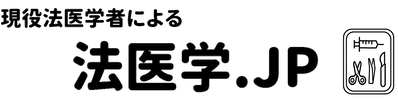令和6年6月30日(日) 午後9時00分〜午後10時00分に、NHKによる法医学の特集が放送されました。

今回はその特集を振り返っていきたいと思います。
…
…
タイトル:NHKスペシャル 法医学者たちの告白(NHKプラス)
『警察や検察から解剖の依頼を受け、死因を判定する法医学者。判断を間違えば、犯罪を見逃したり、えん罪を作り出したりすることにつながる。彼らの仕事は科学的で中立性が高いと信じられてきたが、検察側と弁護側の鑑定結果が対立するケースも少なくない。裁判のやり直し=再審において争点になることも多い。法医学者になる医師も減っている。一体何が起きているのか。法医学者たちの初めての告白から日本の司法制度の課題に迫る。』
1時間という放送時間でしたが、終始、今の法医学が抱える問題を指摘した、大変重いテーマを扱った内容でした。
主に4章に別れており、OPとEDを加えると全6章でした。
順にあらすじを書いていきます。(一部匿名化を行ったり、多少省略した箇所があることをご理解ください。)
…
あらすじ
以下引用始まり
オープニング:〜A教授〜
年間400体もの解剖を行う千葉大学の法医学教授、A教授は歩いて大学へ向かう。
A教授が率いる法医学教室は、日本でも有数の規模を誇る。
しかし、そんな大規模な教室にもかかわらず、ある問題を抱えていた。
それが「解剖数の増加」である。
解剖数が増加したことで、「解剖まで数週間かかってしまう」という事態が起きていた。
特に千葉大学では、丁寧な解剖を心がけていることもあり、1件に数時間かかってしまう。
ただその一方で、警察からは効率化を求められ、現場での苦労が窺える。
…
A教授は、国に対してずっと法医学の人・予算の向上を求めているが、未だに実現には至っていない。
「検視官は3倍に増えているのに、法医学者は全然増えない。法医学は軽視されている」
A教授はそうこぼす。
ドラマでは万能なヒーローとして描かれがちな法医学者も、日々プレッシャーや葛藤に悩まされながら日々業務に当たっているのだった。
…
〜OP タイトルバッグ〜
…
…
第1章:B教授 〜死者の声を聞く〜
B教授は年間250体の解剖を行い、これまで4000体もの解剖に携わってきた、法医学者の中でも2割しかいない女性法医学者である。
「祈ることによる癒やしが無いと、法医学は続けられない」
B教授はそう言って、朝から協会でのお祈りを欠かさない。
年間20万人の異状死のうち、犯罪の疑いがあり、死因が不明の遺体は年間1万体にも及ぶ。
その1万体の遺体に対して司法解剖は行われる。
B教授の部屋には、壁一面に表彰状が飾られている。
薬物を専門とするB教授に対して、全国の警察から多くの依頼が舞い込んでくるのだ。
…
B教授は袴田事件にも関わった。
B教授らが行った実験によって再審が決定された経緯もある。
しかし、それは普段接する警察に対して反旗を翻すような行為でもあり、B教授は引き受けた場合に起こり得る、様々なシチュエーションを想定したと言う。
それでも「法医学者として誠実にありたい」との想いから、その裁判を引き受けたのだった。
…
ある日、路上で亡くなっていた遺体の解剖依頼が来た。
司法解剖の決定は検視官によって行われ、遺体の情報も警察からもたらされる。
解剖の前のCT検査を行ったところ、B教授は頭蓋内にくも膜下出血があるのを見つけた。
これは、他殺か自殺か事故死か?
取材者はそう考えながら解剖に立会した。
…
解剖を進める中で、遺体の頭頂部に骨折があることが発覚した。
この骨折に伴って、くも膜下出血を来したのだった。
しかし、自己転倒によって頭頂部が骨折することは不自然である。
誰かに殴られたのではないか?と疑うものの、警察は「周囲に他人の足跡はなかった」と言う。
解剖の結果、左右心臓血の酸素飽和度に乖離が認められ、B教授はご遺体の死因を低体温症と判断した。
解剖終了後、取材者は「犯罪性は?」と聞くが、B教授は「それは捜査機関が決めることで、解剖からわかることは限られており、私たちにはわからない」と淡々と答える。
取材者が「ドラマでは、法医学者は何でもわかるイメージですが…」と続けるも、B教授は、
「それは大きな誤解。実際は全然そんなことはない。現実はそんなもの。むしろ『わかる』という方がおかしい。無理だ」と言うのだった。
「間違った判断は、犯罪見逃しや冤罪を生みかねない」というプレッシャーの中、B教授は日々解剖を行っている。
…
…
第2章:A教授 〜法医学の危うさ〜
A教授は毎朝徒歩で通勤する。
仕事のストレスによって不眠症を発症したことをきっかけに、徒歩通勤を始めたと言う。
冒頭にあるように、国に法医学への支援を求めてきたが一向に進まない。
A教授の母校は、法医学教室の中で最も歴史のある東京大学だった。
A教授が助手だった頃、法医学者の立場の危うさを感じる事件を経験した。
1996年に起きた【足立区首なし殺人事件】である。
…
首締めによる殺人を疑う警察に対して、執刀したAは死因は判定不可と判断した。
死因の特定に拘る警察は、別の法医学者に死因の調査を依頼した。
その法医学者は、Aの先輩に当たる東大元教授のCだったのだ。
C元教授は組織所見から、死因を首締めによる殺人を主張した。
しかし、その後、見つかっていなかった頭部があるアパートの下から発見された。
そして、そのアパート住民の男が逮捕され、バットで頭部を殴ったことを自白した。
発見された頭蓋骨にも骨折があり、その自白の信用性が認められた。
結果的にC元教授の判断は誤りだったのである。
「今でも時々我々は体験する話です」
そうA教授は語る。
「『そこまで言えません』と言っても、警察は別の鑑定人のところに持って行き、『殺人です』という鑑定を出す」
そんなケースが今でもあるそうだ。
…
法医学者は、検察側・弁護側、どちらの依頼でも裁判での証言を求められることがある。
その中で、法医学者は「脆弱な法医学は悪いような使われ方をされるかもしれない」というプレッシャーを日々感じている。
A教授がそれを痛感した事件が、栃木県で起きた【今市事件】だった。
…
2005年、栃木県の旧今市市で小学1年生の刺殺され、遺体が茨城県の山林で発見された。
事件発生から9年後、被疑者が捕まった。
被疑者は当初取り調べを受けて犯行を自白したものの、裁判の開始前に「自白を強要された」と無実を訴えたのだ。
裁判での争点は、【殺害場所】と【死亡推定時刻】の2点だった。
解剖結果から、遺体の体内から1Lもの出血があったことが判明したが、殺害現場とされた山林の写真には、その出血量に見合う血溜まりは認められなかった。
このことから、弁護団は「殺害現場は山林ではない」と主張した。
一方で検察は、広く反応を示したルミノール発光の写真を法廷に提出し、大量の出血があったと主張した。
この裁判で、A教授は検察側証人として出廷した。
ルミノール発光の現場写真に対して意見を求められたA教授は、実は躊躇いを感じていた。
ルミノールには、(森の中にも存在する)鉄があれば反応してしまうという限界があるからだった。
「このルミノール反応が本当に血液に反応しているとすれば、それなりに広い範囲に血液が落ちている印象は受ける」
A教授は法廷でそう答えた。
…
死亡推定時刻についても、A教授は意見を求められた。
解剖時、遺体の胃の中に未消化の食べ物が残っていた。
このことから、弁護側は、食事の翌日に殺害したとする被告人の自白には矛盾があると主張した。
これに対して検察側は、A教授に対してこの矛盾について尋ねた。
「食後経過時間は当てにならない」
地下鉄サリン事件の発生から1年以上後になって、その被害者を解剖し、事件当日の食事がまだ胃内に残っていたという経験を過去にしたA教授にとっては、それが答えだった。
「食後経過時間は分からない。ただそれが伸びることは実際にある」
A教授は、そう言って当時を振り返った。
…
法廷でA教授は、こんなことも弁護士から言われた。
「分からない分からないでは、法医学なんて不要なのでは?」
それに対してA教授は、
「でも、法医学はそういう世界です。分からないことは分からないと言うしかない」
そう答えるしかなかった。
…
「我々はドラえもんみたいに期待されているんだなと思う時があるんです」
A教授はそう話す。
「他の法医学者は分からないが、自分には分かる」そういった法医学者には、検察側・弁護側、両者から多くの依頼が来るのだという。
…
最終的に、第一審では、自白は信頼できると判断された。
その判決では、A教授の証言のうち「単なる滴下痕としては説明できない相当量の血液が残っている」という部分のみが採用され、「本当に血液に反応しているなら」という部分は盛り込まれなかった。
また死亡推定時刻(食後経過時間)に関しても、判決では「消化活動がほぼ停止していた状態であってもおかしくない」と、A教授の言う「食後経過時間が伸びることはある」という部分だけ切り取られてしまい、弁護側の主張を否定し、検察側の主張を認めるように編集されてしまったのだ。
…
このように、検察側であれ、弁護側であれ、裁判において法医学は、都合の良く編集されてしまうリスクを孕んでいる。
そうした中で、
「唯一心のよりどころとなるのは、法医学の“科学性”しかない。それを蔑ろにしてしまったら、自分が本当に法医学をやっているのかわからなくなってしまう」
と、A教授は言う。
…
…
第3章:D名誉教授 〜“無視される”法医学〜
D名誉教授は、A教授の先代教授であり、東京大学の名誉教授でもある。
前述の今市事件において、控訴審で弁護側証人を引き受けたのが、このD名誉教授だった。
D名誉教授は、東大の退官後に今市事件の証人を引き受けた。
しかし、その後から捜査機関の態度が変わったという。
「“弁護側の法医学者”というレッテルが貼られた気がする」
「(異動先の東京医大で)解剖の依頼が止まり、つらかった」
D名誉教授は当時をそう振り返った。
…
D名誉教授が現場の写真を見たところ、被告の自白通りだとすると、あまりに現場の血痕が少ない。
さらにD名誉教授は、ドイツの血痕学の権威にこの写真について手紙を送った。
すると、すぐに返事が返ってきた。
『血溜まりはなく、写真の中の最も大きな血痕でもせいぜい数ミリリットル以下であろう』
それを確認したD名誉教授は、「山林は殺害現場ではないだろう」と確信した。
さらにD名誉教授は追加実験を行った。
本物の血液を実際の斜面に撒き、一昼夜放置した後に、その染み込みを観察したのだ。
結果は、血液に全く変化は見られず、地面に染み込んですらなかった。
しかし、検察にはルミノール反応という強い証拠があった。
D名誉教授は、試しに血液を撒かずに落ち葉にルミノール試薬を振りかけてみた。
すると、血液が存在しないにも関わらず、検察が提出した写真のように、落ち葉が光ったのである。
落ち葉に含まれている酸化鉄が、ルミノール試薬に反応したためであり、第一審でA教授が言った「本当血液にならば…」という留保は重要だったである。
これらの結果から、D名誉教授は控訴審で、検察側の主張に対する矛盾を立証できたと感じていた。
しかし、検察官はこれを受けて、殺害現場と殺害時刻を大きく変更させた。
控訴審判決では、裁判官は、D医師等の主張を踏まえて、「殺害現場は(当初の)山林ではない」としたものの、殺害したという被疑者の自白の信用性については認めた。
判決は無期懲役だった。
…
「日本の裁判は、海外から“中世並み”や“暗黒裁判”と言われるが、まさにその通りだ」
と、D名誉教授は憤る。
結局、最高裁では上告棄却され、無期懲役が確定した。
無実を訴える受刑者に対し、現在弁護団は再審請求を準備している。
…
…
第4章:E監察医 ~日本を飛び出した法医学者~
E監察医は、33歳の時に日本の法医学に見切りをつけ、アメリカへ渡った。
現在E監察医は、ホノルル市の予算で運営される監察医事務所で所長を務める。
2人の医師と11人の捜査官を率いて、24時間体制で警察からの依頼に対応している。
捜査官は強制力のある捜査権を持ち、死因の究明に必要な情報を独自に集めることが可能だ。
「犯人逮捕」を目的とする警察官とは違い、監察医では「自殺か?他殺か?」を判断する。
また「解剖するか?どうか?」の判断まで監察医が行う。
…
取材中、殺人事件が起きた。
日本の監察医は現場に向かうことはないが、ホノルルでは違う。
E監察医は現場に向かった。
遺体の捜査に関して、捜査官は警察官よりも優先される。
警察官は、捜査官が来るまで遺体を動かすことさえ許されないのだ。
現場では「監察医が死因を決めること」が徹底されており、それ以上のことは聞かれても答える義務もない。
凶器の特定も監察医の仕事ではない。
E監察医によると、アメリカでは、死亡推定時刻すら“科学的根拠に薄い”という評価だという。
…
また別の事件では、海岸で刺し傷のあるご遺体が発見された。
E監察医が執刀し、溺死の所見も認められることから、死因には溺死と刺創の両方を組み入れ、他殺と判断した。
その裁判の前に、弁護士から電話が掛かってきた。
死因について、鑑定書に書かれている以上の情報をE監察医から聞くためだった。
E監察医はそれらの質問に全て答えた。
このように、ホノルルでは、検察側の証人が弁護士へ情報提供することが推奨されているという。
取材を受けたホノルルの検察官は言う。
「監察医は中立で客観的な専門家である。完全に独立しており、(検察や警察との)上下はない」
ホノルルでやりがいを感じているD医師は、与えられた情報だけでなく、自分の好きに捜査し集めた情報でやれることから、「恵まれている」と話す。
そしてまた日本に帰ると、それらが損なわれる可能性にも触れた。
…
…
エンディング:~A教授~
警察から効率化を求められていたA教授は、NPO法人を立ち上げるなどし、何とか受け入れ体制を整えてきた。
しかし、それにも限界があった。
ある日、警察が話をしにやってきた。
「来年度以降、(千葉大学ではなく)東京で別の大学と(解剖の)契約することも視野に入れています」とのことだった。
受け入れ体制を整えてきたA教授にとって、それはとても残念な話だった。
「『(解剖時間が)早くて(解剖費用も)安いところに持って行く』と宣言されたと思った」
そんなスタッフの言葉にA教授も肩を落とす。
解剖数が減ってしまうと、研究や教育にも影響が出かねない。
結局A教授は、一部の解剖の効率化を進め、解剖の受け入れを更に増やすことを決めた。
…
日本では毎年9000人が医師となるが、法医学を目指すのは僅か数人に過ぎない。
「何だこの国」「将来が真っ暗になった」そんな言葉がA教授の口からこぼれた。
「これから社会はどうなってしまのでしょうか?」
そんな取材者の質問に対して、A教授は、
「冤罪や犯罪見逃しが増えたと感じることが多くなるのではないか」と話した。
そして「自分のことと思える人がほとんどいないですよね」
そう言って、雨の中、今日もA教授は歩いていく。
…
…
~ED タイトルバック~
以上引用終わり
…
感想
以上が全編のあらすじとなります。
映像でないと伝わらないことが多くあるので、是非NHKプラスで観てほしいです。
皆さんは率直にどう感じたでしょうか…?
…
特集の解説
この特集のテーマは、法医学でよく言われる「法医学者不足」ではありません。
更に根深い「日本の死因究明制度の問題点」を取り上げていました。
- 国は法医学に予算を出してくれない
- 法医学者が知り得る情報は警察からもたらされる
- 限られた情報だけでは、法医学者は犯罪性を判断することは到底できない
- 法医学者は検察・警察と対立する証人を引き受けることもある
- 執刀医の判断に納得できない警察は、別の法医学者に鑑定を依頼し、納得できる鑑定結果を受けることがある
- 法医学では不確定なことも多いが、法廷では(検察側・弁護側 共に)その鑑定結果を良いように切り取られることがある
- アメリカでは強力な捜査権を持つ監察医が死因を判断する
- 監察医の捜査は警察より優先される
- 監察医はあくまで中立を貫く存在である
- 法医実務の現場にも限界が近づいており、解剖を効率化をせざるを得ない状況にある
ザッとこんな問題点が挙げられていました。
…
特に私がこの特集で有意義に感じたのは『法医学の限界』に言及した点だと思います。
特集の中にもありましたが、法医学者は万能なヒーローではありません。
むしろ法医学でできることはかなり限られているのです。
情報は基本的に警察から貰ったものだけですし、ご遺体は死後変化の影響を大いに受けるため、確定的なことは言えないことも実際には多いと私自身も感じています。
だからこそ、A教授が弁護士に言われたという「法医学不要論」はかなり衝撃的ではあるのですが、そう思う人が出てくるのも全くおかしくない気がしていました。
…
とは言え、もちろん法医学でもある程度断言できることはあります。
“死因の判断”はその典型例で、解剖を含む死後検索を行った上である程度確からしいことが言えます。
アメリカの監察医がそこだけを業務としているのは、そういう理由もあるのだと思います。
しかし、裁判で争いとなるポイントは、そこ以外のことも多いです。
- 自殺か?他殺か?事故か?
- 殺害現場はどこか?
- 凶器は何か?
- 受傷時に生きていたのか?
こういった点はかなり微妙な判断ですし、法医学者にとっては断定は困難なことも少なくありません。
また警察から得られた情報だけを以て判断することの不安もあります。
(※これは“捏造”という意味ではなく、真に我々が必要とする情報が得られていない恐れがあるため)
これらの判断は、解剖した法医によって判断が変わり得ることもあるくらい微妙なため、警察も「別の法医学者に鑑定を依頼する」という行動に出るのでしょう。
“法医学の限界”は法医学者はもちろん、法曹関係者、引いては一般の方まで、これは理解しておく必要があるように思います。
…
私が個人的に気になったのは『登場した各先生方の表情』です。(これは映像でしか伝わらない…)
- 変わらない国や警察に対して諦めとも思える表情を見せるA教授
- 日々プレッシャーを感じながらも強い意思を持って仕事に挑むB教授
- 自分の実験結果や証言を反故にされたことに憤慨するD名誉教授
- アメリカで有意義に監察医業務をこなして充実しているE監察医
表彰状を貰うことに対してB教授が嬉しそうな表情をしていたのが唯一のポジティブな表情立ったかも知れません。
それくらい終始重苦しい内容の特集ではありました。
同業者として、そういった法医学の先生方の人間らしいところが垣間見えたのは、大変印象深かったです。
…
法医学の課題とその対策
様々な問題を抱える日本の死因究明制度ですが、今後どうしていけば良いのでしょうか。
最も根本的な課題は、今の“死因究明システム”にあります。
現在のような【警察中心の死因究明制度】を変えなければなりません。
現在の日本の制度では、まず警察が犯罪性・事件性を判断した後に、法医学者が解剖し死因を究明します。
そもそもこの順番が逆なのです。
「死因も分からない状況で、犯罪性を判断できるのか?」と私はそう思います。
法医学者の行う解剖は、警察の判断に依存します。
犯罪性があれば司法解剖、なければ調査法解剖(もしくは行政解剖)になります。
しかし、犯罪性がないと判断された場合に解剖になることは決して多くなく、地域によっては、医師による外表検査(=検案)で終了してしまうことの方がむしろ多い地域すらあります。
法医学者が解剖の実施を決めるのではなく、決めるのは警察です。
このように「解剖になるかどうか?」は警察次第なのが実情であり、この【警察中心の試飲救命制度】を変える必要があります。
…
しかし、今あるシステムを変えるのはとても大変です。
法医学会は何年も前から“死因究明医療センター構想”を掲げていますが、正直、実現可能性は全くありません。
今回の特集でもあったように、かの東大+千葉大の教授だった先生が、ずっと要望を出しても変わらないのが今の日本の現実です。
日本という国では、何か実際に問題が起こらないと変わりません。
ですので、語弊はありますが、そういった問題が出た時に、「いかに大きく炎上させるか?」だと私は思うのです。
…
パロマ湯沸器死亡事故や時津風部屋事件の発生、およびそれに対する世間からの批判から、死因究明等推進法と死因・身元調査法のいわゆる“死因究明二法”が成立し、日本の制度は変わりました。
しかし、逆に、以前教授不在の県で満足に解剖ができず問題となったケースが報道されましたが、これはすぐに世間の注目は冷めてしまい、現在も日本には教授不在の法医学教室が存在しています。
両者の重大性は本質的には変わらないにも関わらず、結末が違う理由は、やはり“世間の注目度”だと私は思うのです。
…
前述のように、いくら高名な法医学者の先生が訴えても制度は変わりません。
ですが、世論が訴えれば死因究明制度を変えることができます。
そのためにも、何か問題が表出した際に、『大きく注目を集め、世間に問題提起をし続けること』これが私達にできることだと思います。
…
まとめ
今回は長文に渡って、NHKスペシャルの特集について取り上げました。
私自身も改めて考え直す機会となりましたし、一般の方に至っては「法医学者はそうだったんだ…」と初めて現状を知った人も多いと思います。
この特集が放送されたことは、世間が法医学に関心を持つとても良い機会になったはずです。
取材を受けた先生方に心から敬意を表したいと思います。
様々な問題を抱える日本の死因究明制度ですが、
「法医学に対するこの世間の注目をいかに維持し、問題提起し続けるか?」
我々法医学者も、腐ることなく、根気強くこれを続けていかなければなりません。