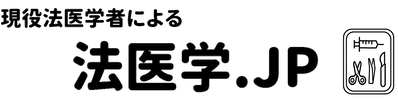先日ネットで頂いた質問に下記のようなものがありました。
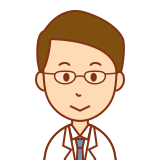
法医学で得た経験は役に立つのですか?
私は素っ気ない人間なので、「私は辞めたことがないので分かりません」なんて答えそうになる…が!
何とかそれらしい答えをひねり出して毎度毎度応えています。
でも、実際のところはどうなのでしょうか?
今回はこの疑問について考えていきたいと思います。
…
【法医学での経験は臨床で役に立つのか?】
実はこの質問は、ネガティブなニュアンスでの質問でした。
「法医学を学んだ後、もし仮に法医学を辞めることになった際、そこまでの経験は、次なる臨床に活かせるものなのか?」
どうやら質問者さんはこうを聞きたかったようです。
…
今年度に入って、私も臨床医を再開させました。
まだまだ臨床医なビギナーな私ではありますが、現時点の実感から言いますと、
【臨床で生かせる知識はあまり多くない】(※あくまで私見)
オブラートに包みましたが、もっと率直に【あまり役に立たない】です。(※あくまで私見)
これが正直な答えだと思います。
…
やっぱり法医学って特殊すぎるんですよ。。
解剖手法なんて知っていても、手術スキルが上がるわけではありませんし(ご遺体は出血しないので)、

“解剖”と“手術”は全く別物です
鑑定書を書く機会なんて、普通の臨床医なら、殆どの先生が一生の中でゼロでしょう。
疾患に関する考え方も、治療を念頭に置いて生きている人を診療する臨床医と比べて、法医学者の思考回路はかなり大きく違います。
なので、私自身、臨床医を再開する際、文字通り「真っ白からのスタート」でした。(厳密に言えば、研修医や院生の頃の臨床バイト以来?)
もう一から勉強し直しですよ。。
…
例えば、糖尿病の患者さんを診て、法医学の経験上「あ、これは行き過ぎると死ぬ病気だ!」と知っていたとしても、
「それが何か患者さんのメリットになるのか?」と問われると、実際は粛々と診療を進めるだけの話ですので、あまり影響はありません。
むしろ、「どのような治療の選択肢があって、そのうちのどれが患者さんにとって良いのか?」ということこそが重要です。
そこが抜け落ちていては、臨床医は務まりませんよね。
…
まぁ、敢えて言うなら、上記のように『疾患に対する危機感』から、
・慎重な診療をするように心掛ける
・患者さんに懇切丁寧な説明をする
ひょっとすると、これくらいのことはあるかも知れません。
「いや、それって臨床医にとって大事なことですよ!」という意見もあると思います。
もちろん、そうです。大事ですよ。
ですが、それを医師として脂の乗った数年間をかけて、法医学者として働く中で学ぼうとするのはかなり非効率的だと言っているのです…。
これは臨床医をしていても、心掛け次第で学べることですし、
「別に法医学者じゃなくて、別の形で学べばいいじゃん」
私はどうしてもそう思ってしまうんですよね。。
…
…
ちなみに、私の周りにも、法医学から離れた医師は幾人かいらっしゃいます。
皆さん、普通に臨床医として働いています。
市中病院に根を生やした先生もいれば、今でも非常勤という形で病院を転々としている(≒ バイト医)先生もいます。
ですので、少なくとも、「法医学者を辞めた後に、臨床医としてもやっていけない」ということは(今の状況においては)全くないです。
ただ私自身は「それまでの経験を次に活かした転職したい」という価値観の人なので、私がその道を進む場合は、きっと苦労が絶えないのだろうと思います。。

「あの数年間は、何だったんだろうなぁ…」と思っちゃいそう。。
「医師として、どういう形の働き方が正解なのか?」は人の価値観によって大きく違いますからね。
まして昨今は「とりあえずやってみて、自分に合わなければすぐ変わる」という考え方の人も多いそうですね。
若いうちに「興味のある分野に一旦足を踏み入れてみる」はアリなのかも知れません。
(法医学の教授を退官した後に、内科医を始めた先生がいると聞いてびっくりしましたが…)

そのバイタリティに頭が下がりますよね
…
…
ということで、【法医学での経験は臨床で役に立つのか?】に対する私の答えは、、、
『あまり役に立たない』です!
…
ちなみに、逆に『臨床経験は法医学で大いに役立つ』これは絶対にあります!
これは多くの法医学者が実感し、言っていることですので、誤解なきよう。
私も何度も言ってますが、法医学に来たいと思う人は、せめて研修医を経てから来ることを強くおすすめしますよー。