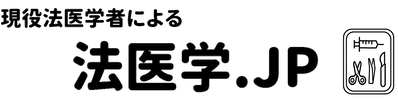“死因”というものはとても複雑です。
それは、死因はなかなか数字で表すことが難しいからです。
…
私はよく「死因の究明は究極のエキスパートオピニオンである」と表現します。
エキスパートオピニオン、、、専門家による意見。
そのエビデンスレベルは決して高い方ではない。。
しかし、これが死因究明の現実なのだと日々感じるのです。
…
…
例えば、DNA型による親子鑑定などは「○○%で親子関係あり」みたいな表現がよくなされます。
計算によって算出され、あとはその数字をどう解釈するか?ということです。
しかし、死因の議論ではそうではありません。
「●●パーセントの確率で死因は××です」みたいな言い方しませんよね?
だって、それなら「じゃあ、100-●●%は、別の死因かも知れないってことじゃん」ってなりますもんね。
そうなると、目の前のご遺体が、その“100-●●%”が起きた可能性だってあるわけです。
単純に「過半数の確率で死因は○○っぽいし、死因それね!」というわけではないのです。
それを理解した上で、死因は何なのか?を考えなければなりません。
ここが死因の難しさなのです。。
…
死亡診断書における死因は原則として『死因は一つの傷病名のみ』を指します。
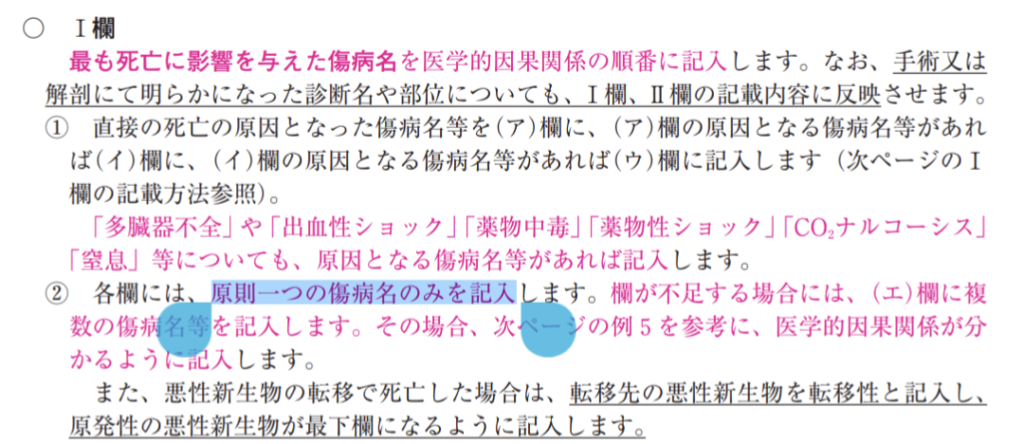
なので、法医学においては、
「○○%の確率で死因は××である」
のような逃げ道?を用意した表現でなく、
「死因は××である」
という認定の下で話が進んでいきます。
従って、時として「0か100か?」のように捉えられてはしまうことも少なくありません。
…
もちろん現実的には、いろんな傷病の複合があったりして、必ずしも1つだけに絞れるわけではありませんが、
その場合でも、往々にして、特に死因に寄与した(最も致命傷となった)傷病名を求められ、対外的にはそれが広い意味での死因と認識されます。
…
死因というものが数字で表せられない以上、それでは死因は誰がどのように判断するのか?
それが、結局は“専門家の意見”、つまりエキスパートオピニオンになってしまうのですね。。
法医学の専門家が、自分の知識と経験を基に、色々な状況や環境を踏まえて判断するのです。
…
…
“エキスパートオピニオン”となると、、、その人がずぶの素人ではない、エキスパートでなければいけません。
それを証明するのが、
・肩書き
・医師免許の有無
・業績
・経験解剖数
・勤続年数
こういうものだったりするんですよね。
逆に、こういったものを持たない人間が意見を言ったところで相手にされないわけです。
そういう意味において、『法医学の中で、いかにエキスパートになるか?』が法医学者には重要となると言えます。
…
…
とは言え、法医学者自身も、好き勝手自分の意見を言うことに満足しているわけではありません。
日々勉強や研究を進め、「いかに科学的・客観的に死因を究明するか?」にも努力しています。
そして、それこそが法医学者がアップデートし続ける意味だと私は思いますね。
…
死因はとても難しいのですッ!!