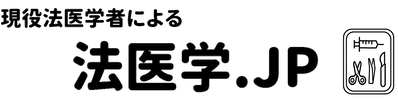“わかる”の閾値は個人によりますよね。
99%理解できていても1%の不明があれば「わからない」と言う人もいれば、51%の理解で「わかった」と判断する人もいます。
これは人によることでしょう。
…
法医学でも似たようなことがあります。
それが“死因不詳”です。
文字通り、死因がわからないと判断した場合に“死因不詳”として死体検案書を発行します。
では、どこまでいけば“わかる”のでしょうか?
…
100%明らか…つまり疑いの余地がなければ→(死因が)わかる
0%…全く検討もつかない→わからない
この2択は簡単でしょう。
しかし、実際の法医学では、この1%~99%の狭間で揺れ動くことがもう必発、、、というか、もうこのシチュエーションしかありません。
そして、この“わかる”の判断は、究極的には法医学者の主観でしかないのです。
同じご遺体でも、ある法医学者がみれば「A」という死因の判断されることもあれば、
別の法医学者がみて「死因不詳」とすることも全然あり得るのです。
これが『死因を判断する』ということなんですね。
…
…
そんな状況もあるからか、法医学の教科書には「わからない時は“不詳”としなさい!」と書いてある本も多いような気がします。
確かにそうなんですよ。
例えば、重大な事件において、まだ疑いの余地があるのに、過信して誤った死因と判断してしまったら、、、
これは法医学者として、絶対に犯してはならない過ちです。
…
…とは言え、時に(いや、しょっちゅう)死因不詳とされたご遺族の無念さを考えてしまうことがあるのです。
『大切な人が、何故亡くなったかわからない』
これほどむなしいことはあるのでしょうか。。
…
「自分が何かしてしまったんじゃないだろうか?」
「自分は何かできたんじゃないか?」
“死因不詳”と付けてしまえば、遺族がそんな終わりのない自責の念に駆られてしまう可能性もあるんですもんね…。
そう考え始めると、、、やはりできる限り“死因不詳”にはしたくないと私は思ってしまいます。。
もちろん、そのような同情に耐えかねて過ちを犯すようなことはしませんが。
…
そんなことを考えて込んでいくと、、、結局我々法医学者ができるのは、
「できるだけ“死因不詳”とならないよう、少しでも重要な所見を見逃さぬよう、真摯にご遺体と向き合うしかない」
これだけだという結論にたどり着くのです。